『臓器農場』
帚木蓬生(新潮文庫、1996)
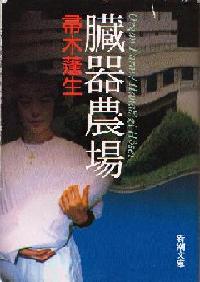 著者は、東大仏文科からTBS勤務ののち、九大医学部に転身し、精神神経科の医者のかたわら、医療を通して現代に生きるということを問う一連の小説を執筆している。『臓器農場』は、九州のとある総合病院を舞台とした、臓器移植をめぐっての医者や看護婦、患者の葛藤を描き、医療の暗部を剔りだしたサスペンス小説である。無脳症の胎児から臓器を移植し、難病の子どもたちを救う。誰もが反論できないような人助けの医療行為。しかし、そこでは無脳症の胎児の「いのち」はまったく顧みられることはなかった。
この小説が書かれたのち、脳死は人の死という法案が国会を通過した。脳死は人の死ということは、無脳症の胎児、新生児はもはや人ではなく、物体に過ぎないということになる。母を脳死状態ののちに亡くしたある学生が、「決してあのとき母は死んでいなかった」と強く語った。わたしたちにとって親密な人の死を、国家によって、あるいは専門家によって一方的に線引きされることに、わたしは違和感を覚える。この小説は、医学の専門家である著者の知見を生かしながら、人を救う努力が人を排除することにつながる現代の医療のアポリアを見事に描いている。
著者は、東大仏文科からTBS勤務ののち、九大医学部に転身し、精神神経科の医者のかたわら、医療を通して現代に生きるということを問う一連の小説を執筆している。『臓器農場』は、九州のとある総合病院を舞台とした、臓器移植をめぐっての医者や看護婦、患者の葛藤を描き、医療の暗部を剔りだしたサスペンス小説である。無脳症の胎児から臓器を移植し、難病の子どもたちを救う。誰もが反論できないような人助けの医療行為。しかし、そこでは無脳症の胎児の「いのち」はまったく顧みられることはなかった。
この小説が書かれたのち、脳死は人の死という法案が国会を通過した。脳死は人の死ということは、無脳症の胎児、新生児はもはや人ではなく、物体に過ぎないということになる。母を脳死状態ののちに亡くしたある学生が、「決してあのとき母は死んでいなかった」と強く語った。わたしたちにとって親密な人の死を、国家によって、あるいは専門家によって一方的に線引きされることに、わたしは違和感を覚える。この小説は、医学の専門家である著者の知見を生かしながら、人を救う努力が人を排除することにつながる現代の医療のアポリアを見事に描いている。

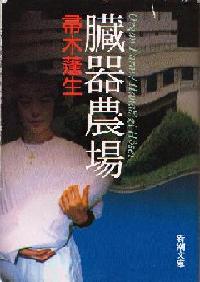 著者は、東大仏文科からTBS勤務ののち、九大医学部に転身し、精神神経科の医者のかたわら、医療を通して現代に生きるということを問う一連の小説を執筆している。『臓器農場』は、九州のとある総合病院を舞台とした、臓器移植をめぐっての医者や看護婦、患者の葛藤を描き、医療の暗部を剔りだしたサスペンス小説である。無脳症の胎児から臓器を移植し、難病の子どもたちを救う。誰もが反論できないような人助けの医療行為。しかし、そこでは無脳症の胎児の「いのち」はまったく顧みられることはなかった。
この小説が書かれたのち、脳死は人の死という法案が国会を通過した。脳死は人の死ということは、無脳症の胎児、新生児はもはや人ではなく、物体に過ぎないということになる。母を脳死状態ののちに亡くしたある学生が、「決してあのとき母は死んでいなかった」と強く語った。わたしたちにとって親密な人の死を、国家によって、あるいは専門家によって一方的に線引きされることに、わたしは違和感を覚える。この小説は、医学の専門家である著者の知見を生かしながら、人を救う努力が人を排除することにつながる現代の医療のアポリアを見事に描いている。
著者は、東大仏文科からTBS勤務ののち、九大医学部に転身し、精神神経科の医者のかたわら、医療を通して現代に生きるということを問う一連の小説を執筆している。『臓器農場』は、九州のとある総合病院を舞台とした、臓器移植をめぐっての医者や看護婦、患者の葛藤を描き、医療の暗部を剔りだしたサスペンス小説である。無脳症の胎児から臓器を移植し、難病の子どもたちを救う。誰もが反論できないような人助けの医療行為。しかし、そこでは無脳症の胎児の「いのち」はまったく顧みられることはなかった。
この小説が書かれたのち、脳死は人の死という法案が国会を通過した。脳死は人の死ということは、無脳症の胎児、新生児はもはや人ではなく、物体に過ぎないということになる。母を脳死状態ののちに亡くしたある学生が、「決してあのとき母は死んでいなかった」と強く語った。わたしたちにとって親密な人の死を、国家によって、あるいは専門家によって一方的に線引きされることに、わたしは違和感を覚える。この小説は、医学の専門家である著者の知見を生かしながら、人を救う努力が人を排除することにつながる現代の医療のアポリアを見事に描いている。
