
#映像企画
田村 和人教授ゼミ
映像制作基礎(演習2年)/
応用(演習3・4年)卒業制作
PROFILE
映像は最強のプレゼンテーション。
じぶんだけでつくれるようになる。
本ゼミでは映像制作の実技を学びます。映像というと、プロの人たちが本格的なカメラや照明機材などを使って作るようなイメージがありますが、本当にそうでしょうか?実際は、最近の身近なIT 機器だけでもプロ並みの映像を作ることが可能なのです。
例えば皆さんが使っているスマホ。新しいスマホであれば、最新の高精細度映像である4K でさえ撮影可能です。また、撮った映像を編集するアプリケーションは、今ではプロとアマチュアの違いはなく同じものを使っています。
ちょっとしたテクニックを身につければ、これらの身近にあるスマホやパソコンを使って、十分に品質の高い映像を作ることができます。「外部の力を借りることなく、自分だけで映像をつくれるようになる」。これが本ゼミのめざしていることです。
今後は会社などでも、映像を活用しながらの、商品やサービスの広報、新企画のプレゼンテーション、あるいはさまざまな報告などがきっと増えていくでしょう。そんな時にこのゼミで培った力がきっと生きるはずです。

#メディアコンテンツ
山下 玲子教授ゼミ
メディアコンテンツの影響の社会心理学的研究/
メディアの影響の社会心理学的研究
PROFILE
身近なメディアとそれにまつわる
社会的現象を心理学の視点から
考えていこう
私たちの日々の生活は、たくさんのメディアにかこまれています。メディアといえば、ニュースがまず頭に浮かぶかもしれませんが、メディアを研究する際にその対象となるのは、そういう「硬い」ものばかりではありません。アニメ、マンガ、ドラマ、映画、音楽、SNSなど、若者におなじみのメディアやメディアコンテンツも、突き詰めてみると、たくさんの「なぜ」「どうして」を生み出します。山下ゼミは、この身近な疑問に、社会心理学の観点から切り込んでいきます。ただ理論的にながめるだけでなく、実際にメディアコンテンツを内容分析し、アンケート調査を行い、さらに、時には実験的手法も用いて、メディアと人々との関係性を明らかにすることをめざしています。そのために、2 年次には社会心理学の基礎と研究法を学び、データ分析の実習を行います。3 年次には小グループに分かれ、自分たちの興味・関心にあわせたテーマを設定し、データ収集と分析、ゼミ合宿を経て、レポート執筆を行います。それを踏まえ、4 年次には個人での卒業論文へとつなげていきます。

#コミュニケーションデザイン
大岩 直人教授ゼミ
ひとと違うことを
考えられるようになる、ためのゼミ
PROFILE
自分は他人と違う。
自分は他人と同じ。
どちらも正しい。
表現はそこから始まる
まずは、ゼミの名称から疑ってかかってください。そもそも、あなたと他人は根本的に違う人間なのか、それとも、実はそんなに変わらない似た者同士なのか。たやすく「そうか、ひとと違うことをしよう」なんて思わないことです。これからの時代に大切なことは、物事をさまざまな角度から考え大胆に未来を推論できるチカラ、徹底的に解像度を上げて思考するチカラだと思います。そうしたものの見方を鍛え、アイデアを生み出すことに重点を置くのが2 年生、それを形にしてアウトプットするところまでやりきるのが3・4 年生です。アイデアを考えることは時に苦しくてつらい作業です。でも、やっぱり楽しい。広告、デザイン、アート、クリエイティブ・ライティング、編集、写真などに興味があって、アイデアを考えることにヘコたれないひと、大岩ゼミの扉をたたいてみてください。


#データ分析
北村 智教授ゼミ
メディア利用行動研究入門/
メディア利用行動の実証的研究
PROFILE
メディアを理解するとともに
社会の多様性を知る
現代社会はメディアとの関わりが不可欠です。私のゼミではメディアを使う人々の行動と心理について考え、研究に取り組みます。研究のなかで行う社会調査を通じて、人と社会の多様性を理解し、自分の考え方を相対化する力も養います。
ゼミ生のテーマはさまざまです。メディア利用者という観点から、テレビ視聴、ソーシャルメディア利用、人とのコミュニケーション手段、ゲーム、広告など学生たちは自分たちでテーマを決めて研究に取り組んでいます。
ゼミでは学年ごとに学習・研究を行います。2 年生では文献講読を中心に、メディア利用と心理に関わる概念や理論、考え方を学習し、ゼミのなかで意見を交わしながら自分たちの考えも深めます。3 年生では2 年生で深めた考えや学習した成果を元に、グループ研究に取り組みます。このグループ研究は、社会調査法を用いて行い、そのなかでデータ分析の方法や論文の書き方を学びます。そして、4 年生では4 年間の学習成果の総まとめとして、個人による卒業研究に取り組みます。

#企業のグローバル化
小山 健太准教授ゼミ
異文化マネジメント・
国際キャリア開発の研究
PROFILE
グローバルな環境で働く人の
心理を研究する
企業経営のグローバル化が進展しており、今後ますます「外国の人とともに働く」という場面が増えてきます。企業が海外進出する場合はもちろん、国内においても、自社が採用する外国人材や、海外の自社グループの社員などと連携しながら働く必要性はますます高まっていくでしょう。
こうしたグローバルな環境で働く人には、英語の能力に加えて、異文化マネジメントの能力や、国際的な仕事を通じて自身のキャリアを開発していく能力も必要です。しかし、こうした能力についての研究は発展途上で、研究すべきテーマがたくさんあります。
そこで、小山ゼミでは、異文化マネジメントや国際キャリア開発などについて、過去の研究を学んだうえで、ゼミ生が自ら研究テーマを見つけて調査に取り組みます。そして、その研究成果を「国際ビジネス研究インターカレッジ大会(通称:IBインカレ)」という全国大会で発表することをめざします。こうした研究活動から結果的に、卒業後にグローバルに活躍するための実践的な能力も身につけることができます。

#コンテンツツーリズム
中村 忠司教授ゼミ
ツーリズムと社会
―観光学の視点で
社会の様々な現象を論じる―
PROFILE
観光学の視点で、社会を考えてみる。
2030年には世界で18億人が国際観光を行う時代がやってきます。観光は国や地域社会にとって活性化のシンボルであるとともに、市民生活や環境に大きな負荷がかかるなど社会問題にもなっています。
この演習では、社会の様々な側面を観光学の視点で論じることをテーマにしています。授業形態は演習形式で、観光学入門書の輪読のほか、観光をテーマにしたグループワーク、個人研究による卒論を前提としたゼミ論の作成などを行います。また観光は現場を体験することが重要なので、フィールドワーク(参加実費は各自負担)も実施します。フィールドワークでは卒論を意識し、現地での聞き取り調査や資料収集の方法を学びます。2 期が始まるまでに各自調査テーマと方法を設定し、1 次データを収集します。最終的には文献調査と合わせて6000 字程度のゼミ論や調査報告書を作成します。ゼミ論や報告書はゼミの中で数回プレゼンし、卒論の骨格としていきます。
各自が率先して旅行に出かけ、まず楽しもうという気持ちを持って積極的にゼミ活動に取り組むゼミです。

#企業ニュース
駒橋 恵子教授ゼミ
企業の情報発信について/
広報・PR の幅広い概念を理解する
PROFILE
2年次は広報・PR の基礎固め/
3年次は模擬記者発表会で実践演習
2年次ゼミでは新聞や雑誌の企業記事を読んで企業のニュースに慣れることから始め、企業web サイトの比較研究、ニュースリリースと記事の比較、CSR レポートの研究分析などを行います。講義科目と同時に履修することで、広報・PRの基本を身につけます。
3年次ゼミでは新商品開発&模擬の記者会発表会を行います。2019 年度と2020 年度は資生堂の協力を得て、マーケティング部門のUNO(男性用化粧品)のブランドマネジャーと元広報部長に来てもらい、オリエンテーションを受けた後、4グループに分かれて新商品の企画を立てました。ターゲットを決めて、新製品やプロモーションのプランニングを行い、本物そっくりのニュースリリースを作成して、「記者発表会」のプレゼンテーションを行いました。
また、広報をテーマにしたディベートを行います。4テーマに分かれて、賛成派と反対派の2人ずつで競う過程で、広報の課題を理解していきます。同時に企業記事の要約を行い、ゼミ論文も執筆し、年度末にはゼミ論文集を発行します。4年次は各自の卒業研究です。

#フィールドワーク
小林 誠准教授ゼミ
異文化のフィールドワーク/
人間至る所フィールドあり
PROFILE
現場を学ぶ、現場で学ぶ
〜人類学的フィールドワークで体感する
異文化と多様性〜
人が住むこの世界は学びに満ちています。学びとは講義を聞いたり、本を読んだりすることだけではありません。いろいろな場所に行って、見たり、聞いたり、触ったり、食べたり、あるいは、人に会って質問をしたり、いろいろな話を聞いたりすることで私たちはさまざまなことを学べます。そう考えると、この世界は至る所に学びの現場=フィールドがあるでしょう。
いろいろな場所に行けば、実に多様な考えを持った人々がいることに気づくでしょう。グローバル化が進んだ現在、日本においても異なった文化的な背景を持つ人々が増えていますし、性別、年齢、出身地の違いなどに目を向ければ、私たちの身の回りには既に常に異文化/多様性が存在します。身近な異文化/多様性を体験することはこの上ない学びになります。それは自分の視野を広げることであり、常識にとらわれない別の可能性を見出すこともできるでしょう。そして、それはとても楽しいことです。

#インタビュー調査
松永 智子准教授ゼミ
ジャーナリズムにみる「日本の外国人」
PROFILE
読んで、歩いて、考えて
話して鍛える研究の五感
本と格闘し、議論の汗を流して、研究の楽しさを味わうゼミです。4年次に充実した卒業論文を書くことを見据え、テーマ探しと研究のイロハを学びます。
まずは文献講読を通して、「おもしろい」卒論とは何か、研究の手法や枠組み、レジュメを使った発表の方法、議論の仕方についての理解を深めます。多彩なゲスト講師との対話や映画・演劇鑑賞、キャンパス外での実習も取り入れ、体験から得る知識や問題意識の涵養も重視します。
1期は、部分的に英語を含む文献講読を中心に、主として日本社会への海外移住者に関する近現代史を学び、グローバルな人の移動がもたらす社会の変容を、メディアの視点から考えていきます。
2期からは、受講生自らがテーマを設定し調べたことを発表します。ゲスト講師にも学び、メンバーからのコメントを受け、修正しながら、年度末にはレポートとしてまとめてもらいます。このプロセスまるごとが「プレ卒論」。楽しく研究するための基礎力を、仲間とともに鍛えます。

#ビジュアル・エスノグラフィー
大橋 香奈 専任講師ゼミ
〈移動〉の経験をめぐるビジュアル・エスノグラフィー研究
PROFILE
グローバル社会における〈移動〉の経験を、
写真や映像を使って調査し表現する
大橋ゼミが調査研究の対象とする〈移動〉には、身体の移動だけでなく、物の移動、想像による移動、メッセージやイメージの移動などが含まれます。グローバル社会における多種多様な移動、そしてそれらの組み合わせに着目するおもしろさを教えてくれたのは、社会学者のジョン・アーリが書いた『モビリティーズ 移動の社会学』という本です。大橋ゼミでは、アーリの本をはじめ、〈移動〉について考えるための文献を、みんなでディスカッションしながら読み解きます。お互いの読み解き方から学ぶことがたくさんあります。そして文献を通して学ぶだけではなく、「人びとの〈移動〉の経験」について、メンバー自身が調査研究を実践します。その際は、「ビジュアル・エスノグラフィー」というアプローチを使います。これは、写真や映像を使ってフィールドワークやインタビューを行い、調査対象の人びとの経験を協働的に理解し表現することを目指す方法です。成果をフォト・エッセイや映像作品として発表することで、研究を通してコミュニケーションする力を養います。
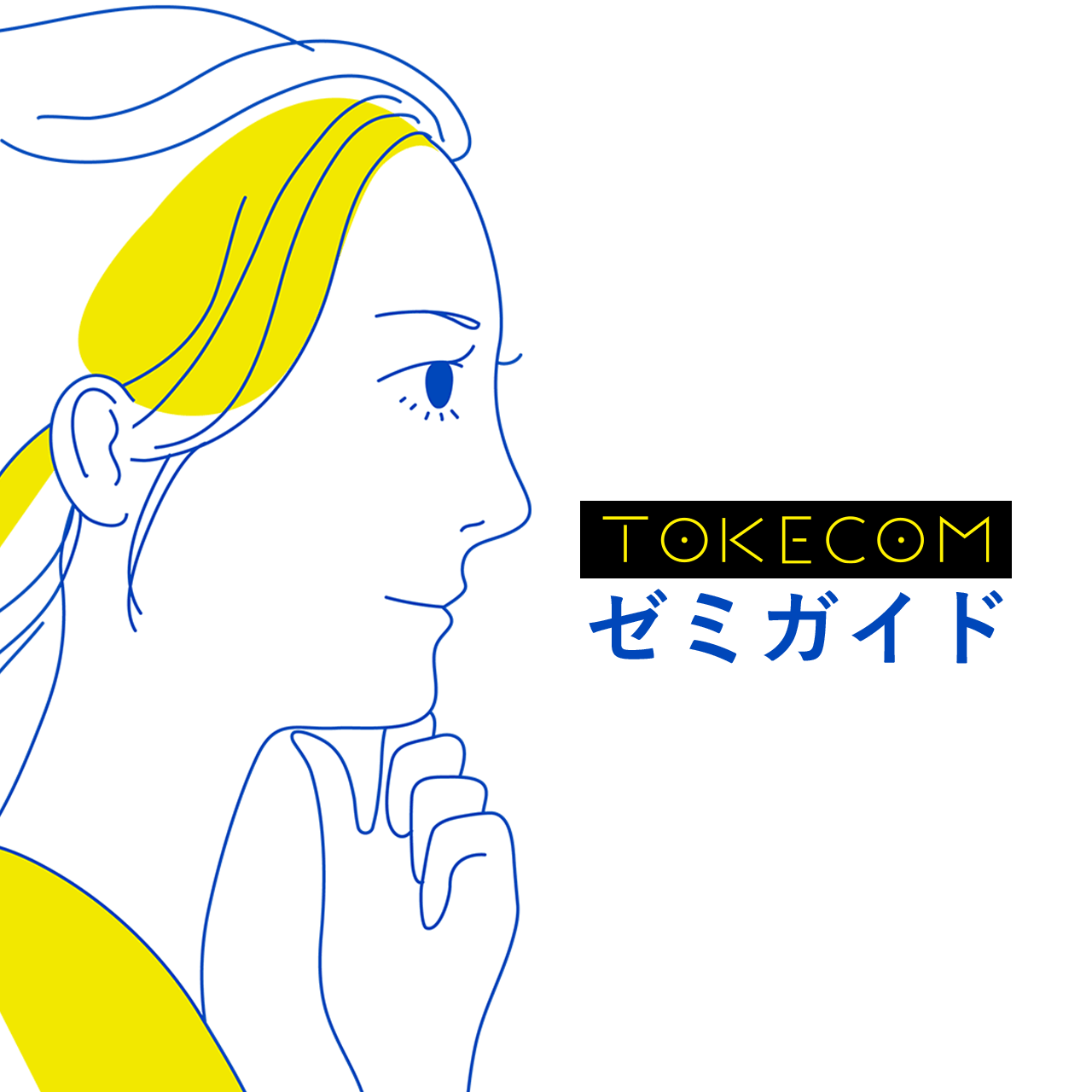
TOKECOM
ゼミガイド考え抜く力を鍛える東経大のゼミ
TOKECOM(コミュニケーション学部)だけで、
20以上のゼミがあります
大学入学後、 誰もが考えるのが、どのゼミに入るベきか。
そしてその先にある将来のこと。
東京経済大学は、建学の理念「進一層」を体現すべく「ゼミする東経大」をテーマに少人数で開講される「ゼミ」にて、講義科目だけでは得られない知識・技能、あるいは思考力・判断力・表現力を育成しています。
TOKECOMのゼミで、未来をひらく学びに出会いましょう!
TOKECOM ゼミガイドのリンクはこちら
TOKECOMで、
世界をコミュニケーションで動かす
学びに出会おう