-
Menu
-
Recommends
-
Access
-
Contact
-
Search

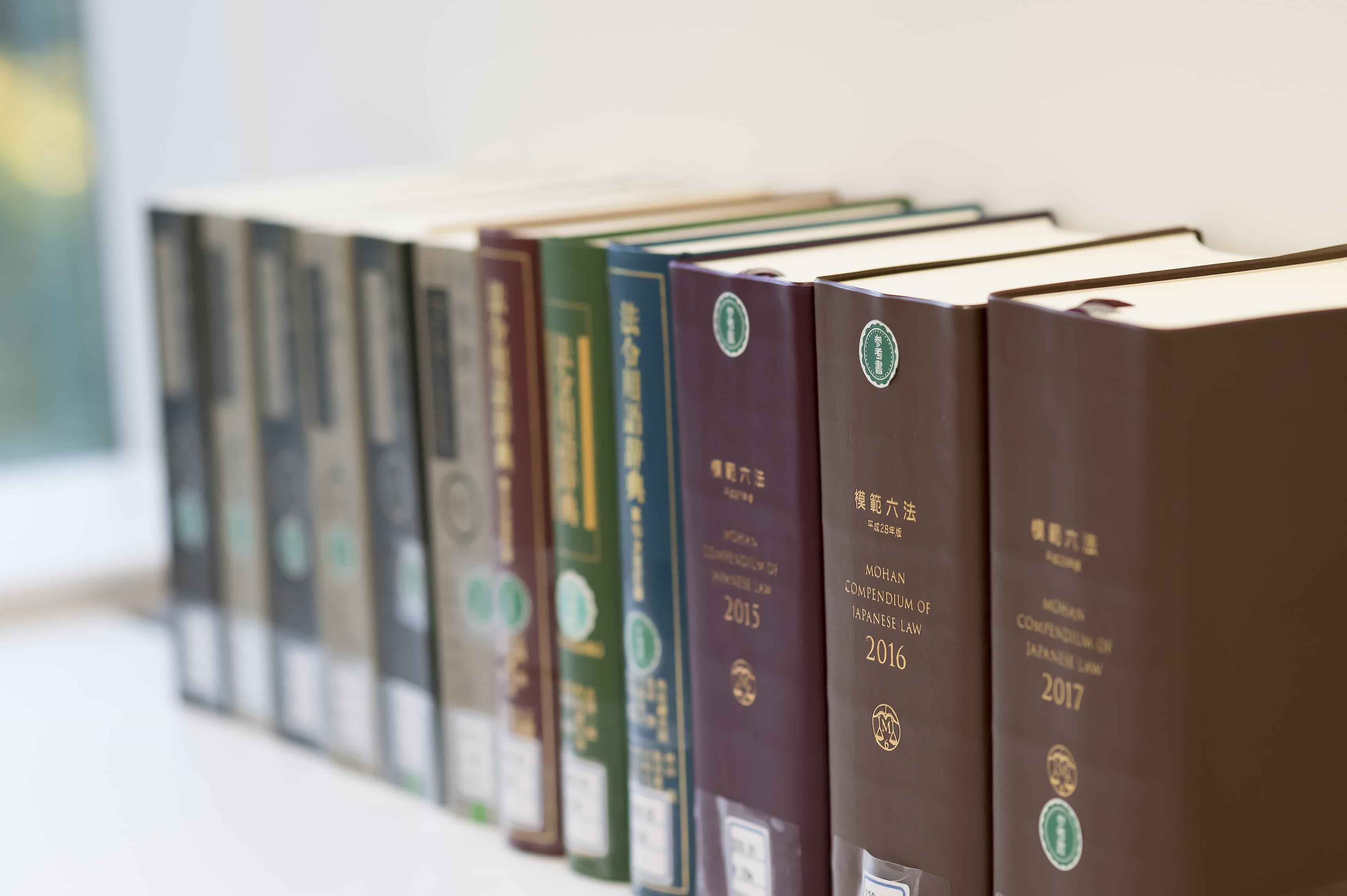
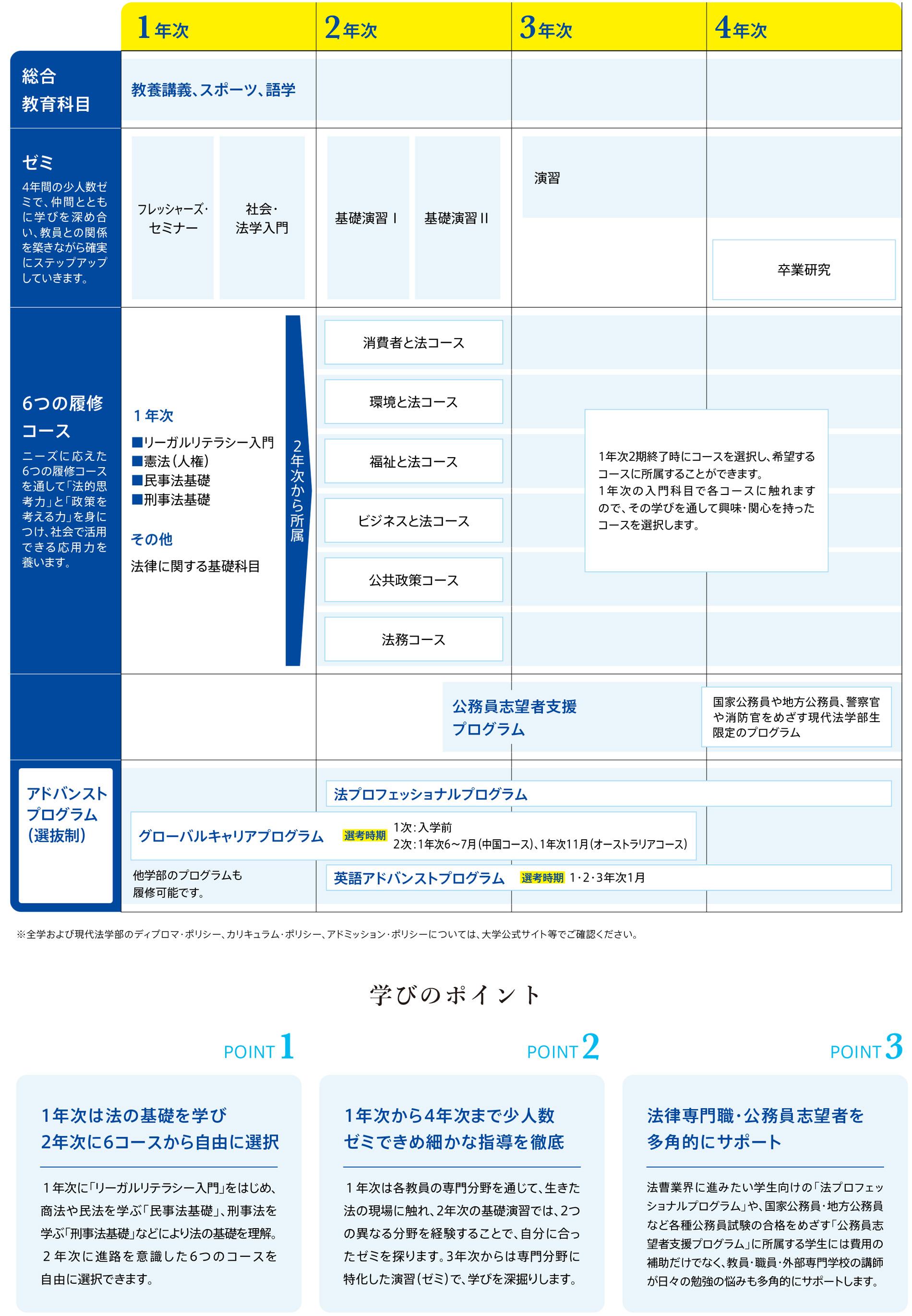

どんな行為が罪になるのか、「犯罪の要件」とそれに対する刑罰の関係をまとめたのが刑法です。例えば殺意を持って人を殺した際に問われる殺人罪。実はこれも条件はかなり緻密です。そもそも「人」の定義とは何でしょう。脳死状態の人から心臓を取り出す行為は殺人なのでしょうか?…答えは私の授業のなかで解説しますね。受講する学生からはよく「こんなに深く議論するとは考えてもなかった」という声が上がります。難しい用語も多いので、授業ではなるべく具体例を示し、理解しやすくするよう心がけています。
実際に起こった事件では、専門家の間でも見解が分かれることがよくあります。判例はそれイコール正解ではありません。授業では、なぜ複数の見方が生まれるのか、どんな筋道で立場が分かれていったのかを考えます。これによって、刑法の知識だけでなく、人生に必要な論理的思考が身につくと考えています。直感で答えに飛びつくのではなく、自分の出した結論をきちんと説明できる社会人になってほしいと考えています。

この授業では、多様な民事裁判手続について、事例を挙げながら、概要を説明します。私自身が裁判官や法改正立案担当官を務めた経験から、「なぜこうした立法になっているのか」「実際の裁判で問題になることは何か」など、なるべく実務的かつ具体的な部分に力点を置いて解説しています。これは法律の専門家をめざす人でなくても、現代に生きるすべての人に必要な学びです。例えば、就職先や取引企業の倒産に遭遇してしまったらどうするか。親戚が遺した空き家をどうすればいいのか。成年後見制度はどのような時に活用できるのか。相続の遺産分割がスムーズにいかないときにはどうするか――。誰もが人生で起こりうるこれらの問題も、この授業で扱う民事手続の範疇です。
学生の皆さんに伝えたいのは、「法律は暗記するものではない」ということです。法律には常に理由があり、ルールは社会の形に応じて変わっていくもの。経済など最新の情勢も理解しながら、私たち一人ひとりが考え続けるべきものだと思うのです。